![]()
トーナメントのゴルフと愉しむゴルフ
= 中部銀次郎 =
1989、90年と二度にわたってマスターズ・トーナメントのテレビ中継でゲスト解説者として『オーガスタ・ナショナル』を見たことがあります。
オーガスタと言えば、世界中のゴルフコースの“設計上の教科書”と見なされ、“世界一美しいコース”と呼ばれているのは私も知っています。どちらかと言えば、戦前に造られた日本の古いコース『廣野』や『東京』で育った私の目からしても、確かにオーガスタは景観の美しいコースでした。
![]()
つま先下がりから、ドローボールが要求されるNo.8
![]()
中部銀次郎氏
コースに立ってプレーするとしたら、あのフェアウェイの起伏、バンカーの形、樹木の枝一本、青い水面、マウンドの大きさ……全てがハザード(障害物)としか見えず、美意識に目覚めている暇など、爪の先ほども生じないと思ったのです。
私がこう申し上げると、読者の中にはきっとこう考える人がいるはずです。「オーガスタは球聖ボビー・ジョーンズと近代設計学の巨匠、アリスター・マッケンジー博士が共同設計した世界一の名コースなのではなかったのか?」
確かにそのとおりです。見た目に自然が美しく、誰がプレーしても愉しいことを目標にしてオーガスタは設計されたと聞いています。
その設計原案の二人の精神は50年以上の歴史を経て、ジョーンズが亡くなった今でも、コースのどこまでも守られているのでしょうが、マスターズというトーナメントの舞台、世界の名プレーヤーが挑戦する時のコースしか見ていない私には、あまりに過酷な条件が在り過ぎると思えてならなかったのです。
ほんの一例をあげれば、2番、10番のフェアウェイにある起伏は、越せるロング・ヒッターにはよりボールが転がりやすく、越せないショート・ヒッターにはランをせず止まるように設定されています。
名物パー3の16番グリーンは全体に池に向かって傾斜しており、池寄りにピンが立った場合、ピンの根元にボールを落とすのはミス・ショットになります。グリーン右にあるバンカーとグリーン・エッジの間を狙い、ボールの自重で傾斜を転がることを計算しなければならないほど、アンジュレーションのある速いグリーンなのです。
こういうアクロバチックなショットの連続で4日間のラウンドをこなすには、我々日本人の想像を絶する体力と精神力が必要で、私には人間業とは思えなかったというのが実感でした。
ただし、オーガスタの会員がプレーを愉しむ普段のコースの表情はもっと違うはずです。
聞くところによると、ジョーンズとマッケンジーの設計主眼は“パーやボギーを狙ってプレーするには易しく、バーディを取るには難しい”ことだったとか。だから、ボール探しでプレーヤーを苛立たせるだけのラフを無くしたマッケンジーの考えには私も賛同します。また、ジョーンズの有名な言葉に、「ゴルフには二種類ある。トーナメントのゴルフと愉しむためのゴルフと」。
このまったく異なる二つのゴルフを一つのコースで全うさせようという発想がコース設計の永遠のテーマだと思うのですが、オーガスタでさえ、そのひとつの回答に過ぎないと私には思えたのです。
![]()
カレドニアンにて、中部銀次郎氏と早川社長
![]()
カレドニアンNo.18
世界レベルのコースを目指す
何故、オーガスタのことを長々と綴ったかと言いますと、この度、縁あって東京グリーンの早川治良社長と面識を頂き、『富里』や『カレドニアン』をプレーした感想を求められた時、私はすぐにオーガスタを連想したからなのです。
特に、カレドニアンにはプレーして愉しく、歯応えのある難度が心地良い範囲で、コース設計の永遠のテーマに対する一つの模範的解答があると思えたのです。
早川社長がアメリカ人設計家のマイケル・ポーレット氏と夜を徹してでも話し合ったと聞いて、二人が“日本に於ける世界レベルのコースを目指した”ということが随所に感じられたからです。山武杉の森を背景にしたグリーンと水面に接するような渚のようなバンカーを見ると、この極めて欧米的な景観の中に、日本人の伝統的美意識の一つに“白砂青松”というものがあるのだから、人間の審美眼には人種の違いはないと思って見ていました。
![]()
クラブハウスにて
ただし、この美観もプレーする時にはハザードとしての別の顔を見せます。
例えば、13番や18番のティショットにはプレーヤー自身の正確なキャリーの飛距離を把握していることを要求されます。その数字によってそれぞれのプレーヤーのターゲットが違ってくるのです。特に、13番のように水面上を通して距離を目測するのは難しい技術の一つです。
18
番もワン・ストロークを争うトーナメントであれば、安全な左のフェアウェイへ4番ウッドで打つところでしょうが、愉しむだけのプレーならばドライバーで水と渚を越すルートに挑むのも一興でしょう。
このように一つのホールに多くの攻略ルートがある設計パターンをストラテジック(戦略型)と言うのでしょうが、普段のカレドニアンには大トーナメントでのオーガスタほど過酷でない範囲で、ルート選択の幅があるホールが多いと感じました。
つまり、プレーヤーを必要以上に困らせたり、難度の高いショットを連続して要求していず、リーズナブル(理に適った)で、フェアに思えました。
フェア・プレーの精神はプレーする側の問題だけでなく、コース設計の側にも必要不可欠なものだと考えます。“トーナメントのゴルフ”をもう終えた私ですが、“愉しむためのゴルフ”をしに、何回でもカレドニアンのティに立ちたいと思っています。
設計者に負けてはダメ、と中部は言った杉山 通敬
挑戦して、一度でも成功したら、成功が成功を呼ぶ
「ああ、よかった」
まるでアベレージ・ゴルファーのようにして中部銀次郎さん(以下敬称略)が安堵の胸をなでおろしたのは、カレドニアン・ゴルフクラブの18番のティショットを打ち終えた時だった。
ご存知のように、中部は日本アマに6回優勝の記録を持つチャンピオン・ゴルファーである。彼が競技界を引退したのは1987年のことで、以後、ひとりのアマチュアとして親しい仲間と「楽しむゴルフ」を心から味わうようになっていた。
といっても、競技ゴルフで培った「1打としてないがしろにしない」プレーぶりは、サマ変わりしたわけではない。格調の高い凛としたゴルフはむしろ、競技ゴルフの時より純度が高まったようにも思えるほどだった。それが空気伝染でもするかのごとく、一緒にプレーするものに伝わり心地よい雰囲気をつくり出す。決して堅苦しいのではない。
「ああ、よかった」と言って胸をなでおろしたのは、ティショットが池を越え、フェアウエイをキープしたからである。ティはバックティではなかったが、池を越すには220ヤードのキャリーが必要であろうことは判断していたとみえ、「ギリギリかな」打つ前に呟いていた。
「久しぶりにちょっとドキドキするな」一緒にプレーしていた連中がみな正真正銘のアベレージ・ゴルファーであったこともありいつになく、彼はくだけた様子であった。
ティショットをフェアウエイにキープしたあと、セカンド・ショットは池の左側のフェアウエイに運び、第3打でグリーンに乗せた。
あとのことは忘れたが、ホールアウト後の19番ホールで彼が言ったことは覚えている。わたしが「ギリギリって、最近のティショットの距離はどのくらいなの?」と尋ねたのが話の始まりだった。酒を飲みながらのことなので舌はなめらか。
「真芯に当たってキャリーは230ヤード。ランを入れて250くらい。ちょっと芯を外れたら220の距離はあぶない。だからドキドキだった。でもね――」
盃の酒を口に含んだあと、さらに言った。「でもね、設計者が越せるものなら越してみな、と言っているときはその挑戦を受けて立つ気になっちゃう。たとえギリギリでもシンさえ食えば充分に越えるんだから、ベストを尽くす気になる。それが好結果につながることがしばしばあるんです」
「逃げちゃいけない」
「自分の飛距離との相談なので、越えないと判断したら逃げるしかない。だけど越えるのに逃げてばかりいたら、越せるものも越せなくなって、その分の楽しみ方も減っちゃう。集中力も高まらないから、逃げたのに中途半端な打ち方をしてかえって池の真中にドボンする。だけど挑戦して、一度でも成功したら、成功が成功を呼ぶ可能性があります」
「無謀と紙一重みたいな気がするけど……」
「確率がゼロ。あるいは10回やって1回しか成功しないようじゃ無謀かもしれないけれど、自分の判断で越せると思ったときは積極的に越せるぞ、と思ったほうがいい。集中力が高まるし、仮に失敗しても原因がどこにあるのか吟味する材料になる。設計者が戦略性を盛り込もうとするのは、プレイヤーの力なり技術なり精神力を引き出そうとしているからなんです」
「逃げてばかりいたら、戦略性なんかない」
「設計者に負けちゃダメです」
一杯やりながらそんな話をした。そう言えば現役時代の中部は、どんな小さな試合でも勝ちたい一心でプレーしたという。人に勝つ。コースに勝つ。自分に克つ。引退後は「人に勝つ」は薄らいだようだが、その分コースと自分には手を抜かなくなったのだ。
ガンに侵され、「楽しむゴルフ」も出来なくなった頃、自分のゴルフ人生を振り返って言ったのを思い出す。「すべては夢でした」
今年は中部銀次郎の七回忌の年である。彼はカレドニアンを好んでいた。
![]()
ベストを尽くして好結果につなげるという
記事一覧に戻る
TOPへ戻る
 つま先下がりから、ドローボールが要求されるNo.8
つま先下がりから、ドローボールが要求されるNo.8
 中部銀次郎氏
中部銀次郎氏
 カレドニアンにて、中部銀次郎氏と早川社長
カレドニアンにて、中部銀次郎氏と早川社長

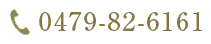



 カレドニアンNo.18
カレドニアンNo.18
 クラブハウスにて
クラブハウスにて
 ベストを尽くして好結果につなげるという
ベストを尽くして好結果につなげるという