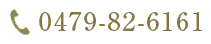西澤 忠
カレドニアンGCのコース設計コンセプトは「スコットランドのリンクスにある」と早川治良社長はいう。その昔、コース造りを模索する過程で、ゴルフ歴史家の摂津茂和氏に教えられたからで、開場以来30年を迎えるコースが当初から、“ワングリーン”を貫いてきたことからもその思想は今日まで貫かれている。ご存知のように、四季のある日本では芝種の違う二つのグリーンを持つ“ツーグリーン”制が常識とされた時期があり、未だに旧式弊害とされながら踏襲しているコースは数多い。東洋系の高麗芝に比べ、西洋芝の管理・維持には費用が嵩み、高度なメンテナンス技術が必要だったからである。
しかし、ベント芝に代表される寒地型西洋芝の進化は目覚ましく、日本のように高温・多湿の気候風土にも十分に耐えられる新種の芝種開発が進み、四季を通して西洋芝グリーンを駆使、ワングリーン運営が可能になった。このため、戦前・戦後に造られた名門コースも急ぎワングリーン化を目指す傾向が現われているのが今日の実情である。その点、カレドニアンGCは当初からスコットランド・リンクスのように、ワングリーンで一貫させて来たことはメンバー諸氏にとって幸いであったろう。
とはいえ、ワングリーンを常に一定の速さと転がりの良さを保つためには幾多の困難を乗り越える苦労があったし、その作業は今でも日夜続けられている。男女プロ・トーナメントの隆盛を見るまでもなく、一般ゴルファーまでもがスティンプメーターで“10フィート以上の速い高速グリーン”を望み、パッティング・クオリティの完璧さを求める声には終りがないからである。
開場当初からグリーン管理に携わって来た石井浩貴キーパーによれば、「J・M・ポーレットの設計した不定形でアンジュレーション豊かなグリーンを管理・育成するには常に時代の要請に向き合う努力が必要です。一般的な“ペンクロス”芝で始め、10年前には“グランプリ”という第三世代の新種を加えてグレードを上げたが、2年前には今度“オーソリティ”に変更しました。グリーン管理は日進月歩で、常により良いクオリティをプレーヤーに提供するためです」と、世界のゴルフ界を見据えた作業が求められると説明する。

思い起こせば、カレドニアンGCでは2000年にプロのメジャー競技、日本プロ選手権を開催した。その時のグリーンは11フィートを超す速さと、ブルーグラス洋芝のラフを20センチに伸ばしたこともあって、佐藤信人プロの優勝スコアが4アンダーという熱戦を生み出したものである。この実績と経験が石井キーパーの自信となり、さらに上のレベルを目指す動機づけになっているに違いない。
ところで、ここカレドニアンGCのグリーンはどの程度の大きさがあるかメンバー諸氏はご存知だろうか? 答えは、平均で606m²あり、中でも最大で742m²(11番、12番)、最小は唯一ツーグリーンの16番で、360m²(左)と325m²となっている。これは全国の平均以下のスモールサイズだが、各ホールのグリーンは最少で4ヵ所以上のホール・ロケーションを確保できる一級品である。名手トム・ワトソンが「私の生まれ育ったカンサスのホーム・コースが小さなグリーンが特長だったので、アイアン・ショットの精度に磨きをかける必要があった」と述懐したものである。つまり、小さいターゲット(目標)に向かって練習していれば、アイアンが上達し、他のコースへ行っても恐れる必要がないというわけだ。
もう一つ、不定形なグリーンに立てるピンの位置は毎日変わるが、これにも一定の法則がある。グリーンを5ヤード刻みに碁盤の目状にラインを想定し、それを4等分にすると右奥の次は左手前、そして右手前の翌日は左奥という具合に5日間で一周するという。ピンが奥へ行った日は、ティ・マークも前に移動するというようにそのホールのヤーデージも一定に保つように配慮する。
さらに、グリーンモアで毎日刈る際にも芝癖をつけない工夫として芝刈りの方向を変えるなどクオリティを保つ工夫には多面的な配慮が必要らしい。世界の名コースの常識だが、高度のクオリティを保つワングリーンにはなんと無尽蔵な汗と涙が埋蔵されていることか。メンバー諸氏にはプレーしたグリーン上のピッチ・マーク修理はもちろん、足を引きずらないなど細心の心がけをぜひともお願いしたいところである。